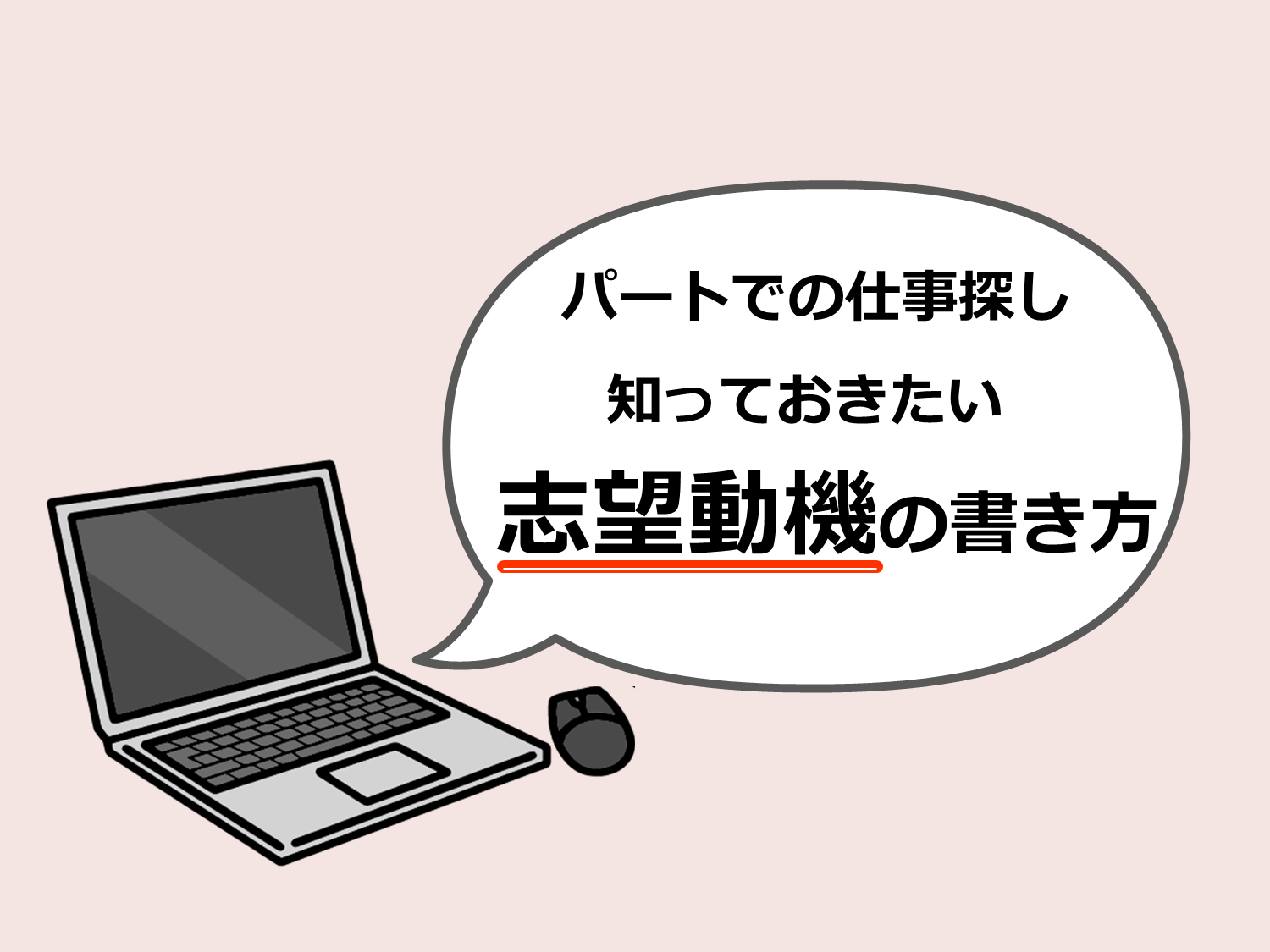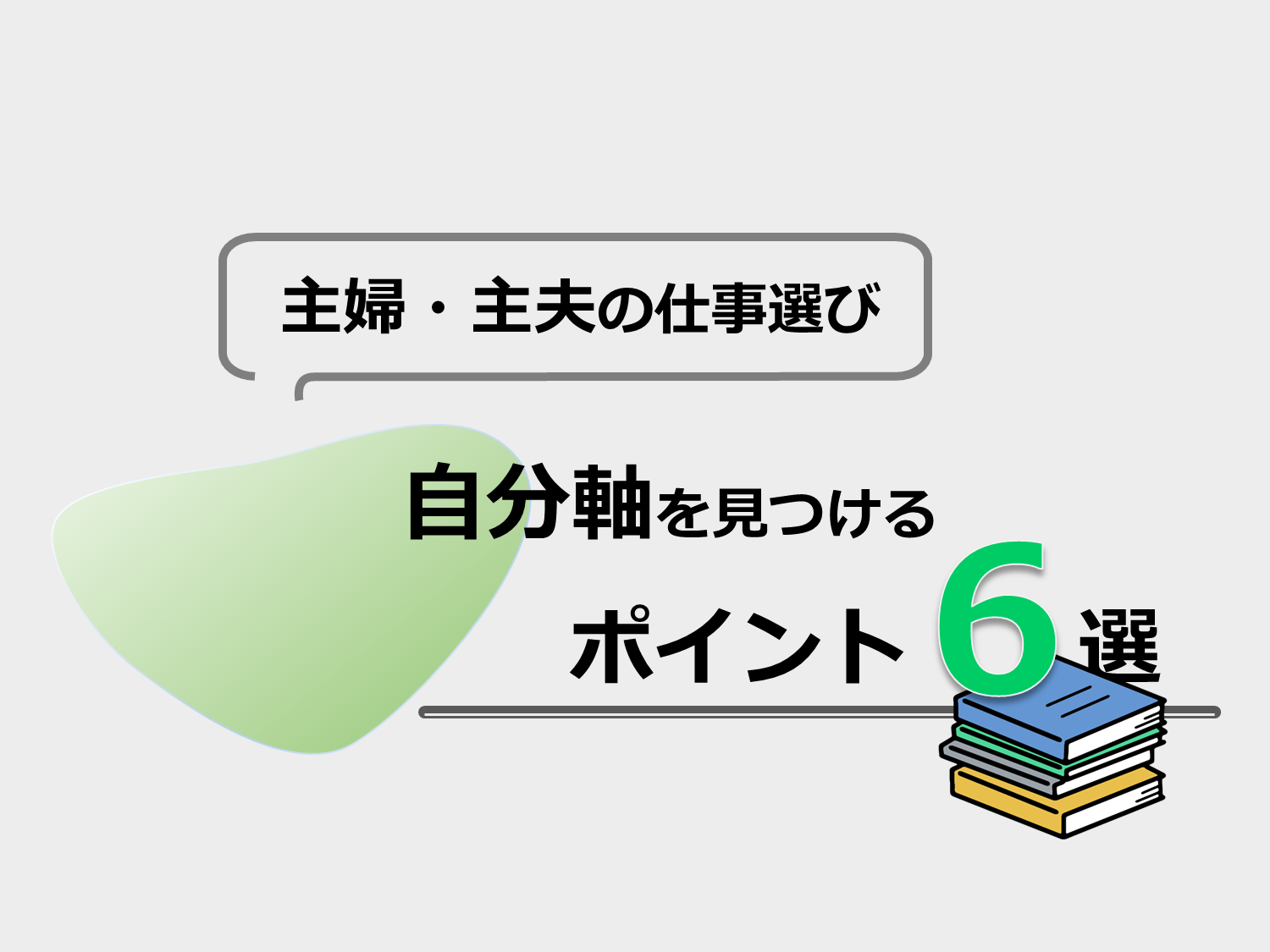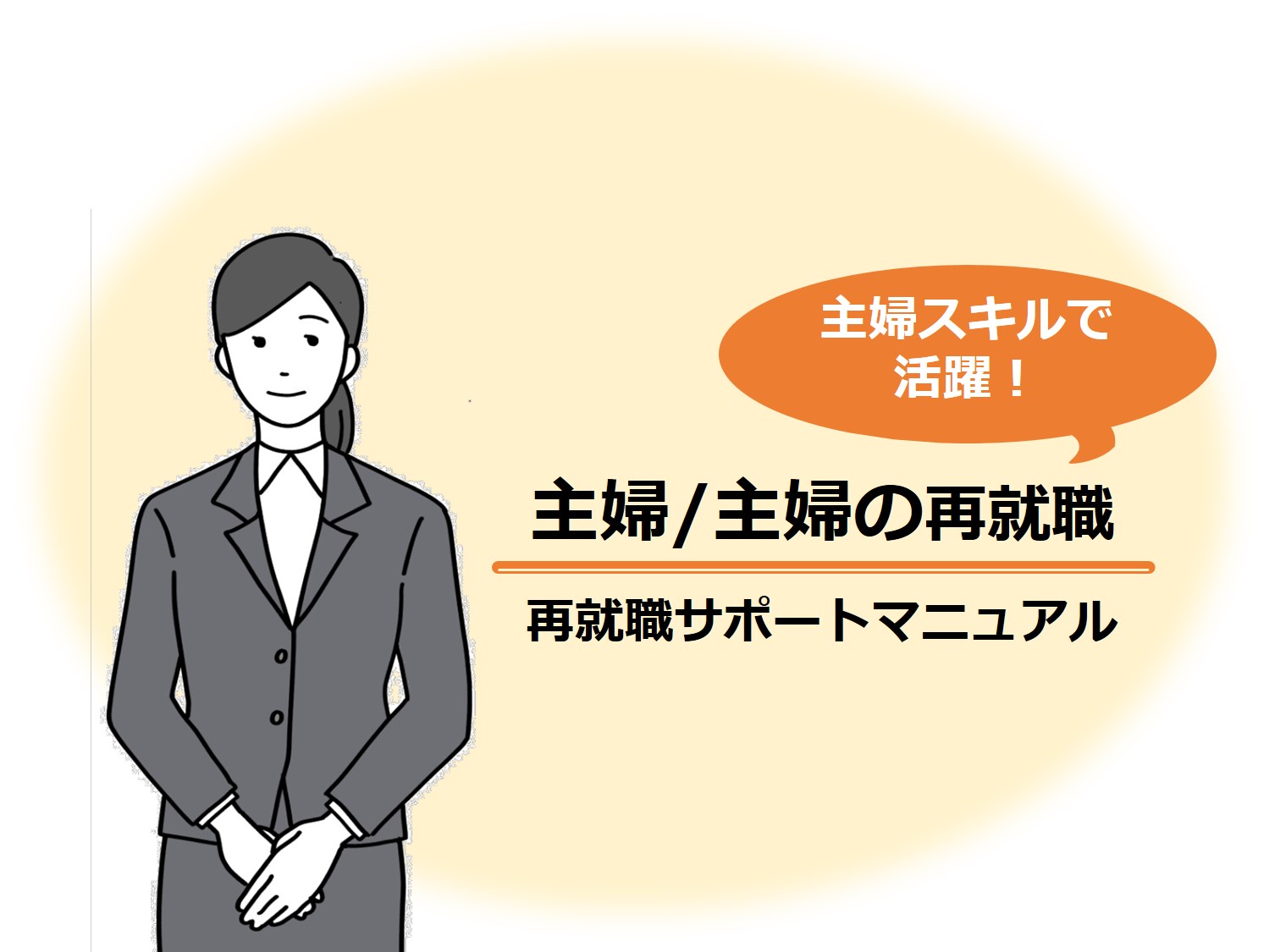
家事と仕事の両立|知る、つながる、働くわたし
【主婦/主夫の再就職】主婦スキルは活かせる!再就職サポートマニュアル
「仕事を始める」「就職する」と思い立った時、あなたは迷わず一歩踏み出せますか?多くの人は、何かしらの不安を抱くものです。特に主婦の方は、仕事のブランクやスキルの面で不安があるのではないでしょうか。「特別な資格やスキルがないけど、就職できるかな」「しばらく仕事から離れていたから、再就職できても職場で活躍できるかな」そんなあなたの再就職への不安を解消できるノウハウについて、幅広くご案内します。主婦/主夫の再就職を成功させるために主婦スキルを活かそう実は!主婦の方の持つ能力は、仕事で役立つものが多いのです。いくつかピックアップしてご紹介します。マルチタスク処理能力(マルチタスキング)マルチタスキングとは、複数の作業を同時に並行して行うことです。日々、様々な家事を同時進行で進める方は、マルチタスクの処理能力があると言えます。人によっては子育てや介護などもあり、多くのことを限られた時間内にこなしているのではないでしょうか。複数のゴールをイメージしながらタスクを進めることは、だれもができることではありません。このスキルは職場でも重宝されます。コミュニケーション力特に子育て中の方は、子供に関連するお付き合いが多いと思います。学校の先生や子供のお友達・同級生の親と、適切な距離感を保ちながら、「ちょうどいい」会話をしているのではないでしょうか。そこで培われたコミュニケーション力は、職場でも確実に活かすことができます。忍耐力・継続力・計画力子育て中の方は、思い通りにいかないことの連続に、日々忍耐力が養われているのではないでしょうか?また、家計管理をされている方は、家族の将来キャッシュフローを見据えて、地道に家計簿をつけていますよね。継続力・計画力が培われているのではないでしょうか?目に見えるものではないこれらの能力も、仕事をする上で重要なスキルと言えます。日々の生活の中で自然と培われているスキルが、思いのほか職場で役立ちます。「何もしてこなかったけど大丈夫かな」と悲観しなくても大丈夫。主婦として過ごした時間と経験は、採用面接でも立派なアピールポイントになります。自信をもって伝えましょう!再就職に不利になる?ブランクと時短勤務の現状一般的に、採用担当者が見ているのは、「自社で求める人材像とマッチするか、活躍できる人か」という点です。そのため、一概に再就職に不利になるとはわけではないのでご安心を。それを踏まえて、皆さんの不安ポイントへの対応について説明します。ブランク会社のニーズとあなたの能力がマッチしていたら、ブランクはさほど問題にはなりません。仮に3年以上の長期ブランクの場合、休職した理由を簡潔に示しましょう。また、ブランク中の経験も積極的にアピールして、働く意欲を示しましょう。時短就職の際、時短の希望だけを伝えるのではなく、時短の中でも「自分が提供できる価値」を示すことが重要です。企業に採用したいと思わせる、あなたの強みをしっかりと伝えましょう。採用担当者の求めるもの=マッチするポイントをよく調べて、過去の職務経歴、ブランク中の経験や「主婦スキル」をアピールしていきましょう。また、応募の際は、正社員だけではなくパート等も含めて、選択肢を広く持つことをお勧めします。条件にこだわりすぎると、思ったような求人がないときに、心が折れてしまいます…これだけは譲れないという点以外は、柔軟な視点でお仕事を探すといいでしょう。再就職市場と主婦/主夫の活躍求人市場について主婦・主夫の方向け求人情報を提供している、しゅふJOBによると、同社会員数、取引社数は年々増加傾向にあります。出典:ビースタイルグループ【しゅふJOB調べ】▼【しゅふJOB】みずほ銀行パート社員募集ページはこちら(勤務地東京特集)しゅふJOB(みずほビジネスパートナー紹介)全体的な傾向として、主婦求職者、求人数の増加が見られます。足元までの全体的な有効求人倍率も見てみましょう。出典:厚生労働省一般職業紹介状況※有効求人倍率=有効求人数を有効求職者数で割って算出。一般的に高い方が仕事は探しやすい・就職しやすい2018年をピークに2020年に大きく下落しています。しゅふJOBデータとの連関は見られませんが、2021年に持ち直し、足元までに徐々に有効求人倍率が伸びてきていることが分かりますね。仕事選びの「自分軸」とは?「求人市場も割といいみたいだし、復職を考えてみようかな。でも、さまざまな求人情報があって、どのような仕事が自分にあっているか、どのような仕事がしたいかわからない」ということがあるかもしれません。そんな時は、「自分軸」を基準にして考えてみましょう。「自分軸」とは、自分にとって大切なものを明らかにした軸のことです。自分軸をもっておくと、自分に合う仕事を見つけやすくなります。では、自分軸はどのような「条件」と「適性」で考えていけばよいのでしょうか。自分軸を考える6つのポイントポイント1勤務時間・休暇条件生活とのバランスポイント2希望収入ライフスタイルに合わせた収入計画ポイント3通勤距離と時間時間管理と効率性ポイント4職場環境雰囲気や働きやすさの確認ポイント5業務内容・スキル・経験自分のスキルに合う仕事ポイント6自分自身の適性チェック自己分析で得られるヒント優先順位のつけ方とステップ自分軸となるポイントが決まったら、気になっている求人情報について自分軸を元に評価してみましょう。「〇・△・×」をつけて点数化し、客観的に見ることで自然と整理されてくるのではないかと思います。自分軸の考え方、活用方法についての詳細は、こちらの記事をご参照ください。【主婦/主夫の復職・再就職】仕事の選び方・仕事選びの軸6選スキルと資格の強化で差をつける自分の希望する求人情報が決まったら、具体的に選考対策を考えてみましょう。もし、希望する職種に応募するライバルがいた場合、関連する資格があると大きなアピールポイントとなります。有利に再就職を進めるための準備「もっと強みを持って、より有利に再就職に臨みたい。資格を持っておきたい。勉強したい」という方は、大学のビジネスプログラムや自治体の職業訓練の活用を検討してみてはいかがでしょう。大学の短期集中ビジネスプログラムビジネス英語をはじめとした、就職に有利な資格や講座を受けることができます。夜間・オンライン授業もあるので、半年間集中で「毎日この時間だけ勉強する!」と決めて取り組んでみるのもいいかもしれません。自治体による職業訓練自治体が提供する職業訓練では、再就職をサポートする制度が多数あります。中には、再就職を目指す女性向けコースと限定しているものや、託児サービス付きの講座もあります。基本的には無料(教科書代等は実費)で、事務スキルの基本や人気の資格も学べる、大変お得な制度です。主婦に役立つ資格自宅にいながら、スキルアップできることのひとつに、資格取得があります。身近な資格から難易度の高いものまでさまざまですが、事務職で働きたい!と考えたときに、家事育児をしながらでも修得しやすく、仕事や実生活でも役立つおすすめの資格をご紹介します。簿記検定企業が日々行う経営活動を記録・計算・整理し、企業の経営成績と財政状態を明らかにする業務を行う資格ファイナンシャルプランナー検定一人ひとりの将来の夢や目標に対し、お金の面でのさまざまな悩みについて解決策をアドバイスする専門家ITパスポート検定ITを利活用するすべての社会人・これから社会人になる学生が備えておくべきITに関する基礎的な知識を証明できる国家試験家事・育児と資格勉強の両立日々の家事・育児に追われての勉強はなかなか難しいもの。少しでも興味を持てる資格について、毎日少しずつでも進めていくことが資格取得の近道になります。その他おすすめの資格や、資格勉強の体験談など、詳細はこちらの記事をご確認ください。パートの志望動機、書き方のコツとは?相手に伝わる志望動機を書こう。再就職までの4ステップガイドSTEP1:自己分析先ほどの仕事を選ぶための「自分軸」に加えて、自分自身の強みやスキル、仕事を通じて実現したいことを整理しましょう。自己分析ができれば、志望動機が明確になります。志望動機の考え方については、こちらの記事でも紹介しています。パートの志望動機、書き方のコツとは?相手に伝わる志望動機を書こう。STEP2:求人サイトに登録やりたいことが見えてきたら、実際に求人サイトに登録してみましょう。求人サイトはそれぞれ対象とする求職者によって、紹介する会社の種類や業務内容が異なります。みずほビジネスパートナーは、主婦の方にお勧めの企業を多数ご用意しています。みずほビジネスパートナーでお仕事を探すメリット求職者へのきめ細かい対応が可能履歴書の志望動機やアピールできる職歴書の書き方をアドバイス!求人企業の了解がとれた場合は、企業との面談にビジネスパートナーが同行・同席するケースも!銀行子会社の紹介という信頼感、安心感ご紹介企業はみずほグループやお取引先が中心!みずほビジネスパートナーのエントリーはこちらSTEP3:履歴書・職務経歴書の書き方就職サイトへの登録後、いよいよ企業にエントリーします。履歴書・職務経歴書の具体的な書き方はこちらで説明しています。履歴書・職務経歴書の書き方職務経歴書の書き方ポイントはこちらの記事で紹介しています。再就職時の職務経歴書の書き方は?前職・スキルのアピール、ブランクの伝え方を解説STEP4:いざ面接へ書類選考が通ったら面接です。求人サイトのエージェントとも相談して、面接対策を行いましょう。みずほビジネスパートナーでは、面接でアピールすべきスキルや経験、特性などもしっかりとアドバイスします。不安なことがあればぜひご相談ください。【就活メール&面接マナー】メールの書き方の基本から面接時のマナーまでまとめいかがでしたでしょうか。しばらくお仕事から離れていると、再就職を考えるときに不安になってしまいますよね。でも、主婦の経験を持つ、あなたならではの「主婦スキル」があります。その経験はお仕事で必ず役に立ちます。まずは、ご自身を分析してみることで、自分に合った仕事や、再就職への道筋が見えてくるのではないでしょうか。みずほビジネスパートナーは、あなたの不安に寄り添い、丁寧にサポートを行います。ぜひ登録を検討してみてください!関連記事パートの志望動機、書き方のコツとは?相手に伝わる志望動機を書こう。再就職時の職務経歴書の書き方は?前職・スキルのアピール、ブランクの伝え方を解説【就活メール&面接マナー】メールの書き方の基本から面接時のマナーまであなたのお仕事探しに有益な情報をお知らせします!LINEのお友達追加をよろしくお願いいたします!みずほビジネスパートナーで仕事探し(LINE)