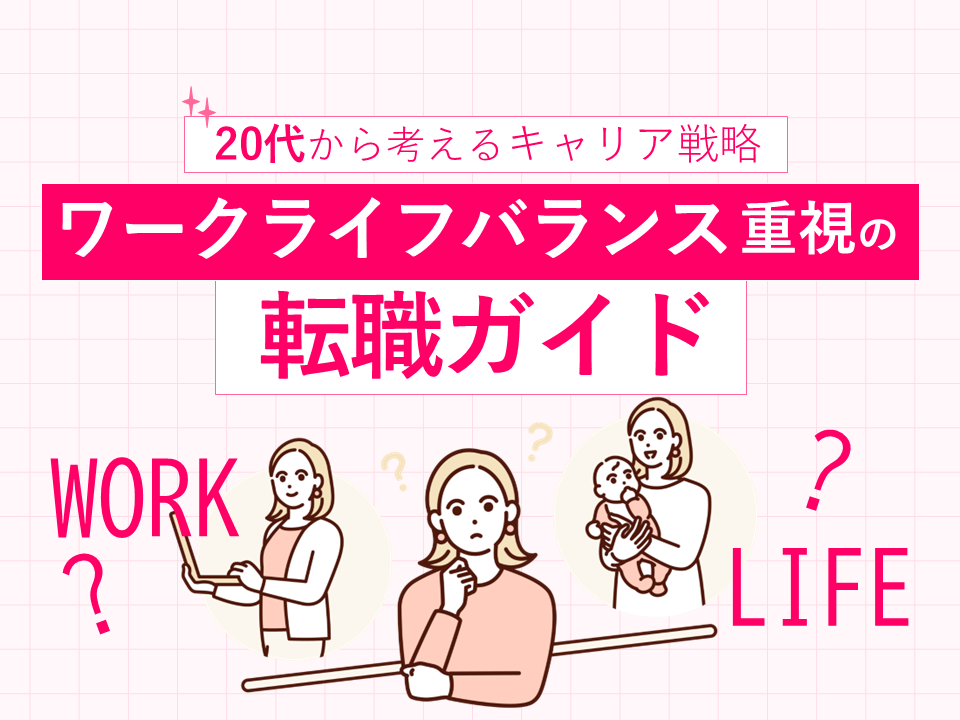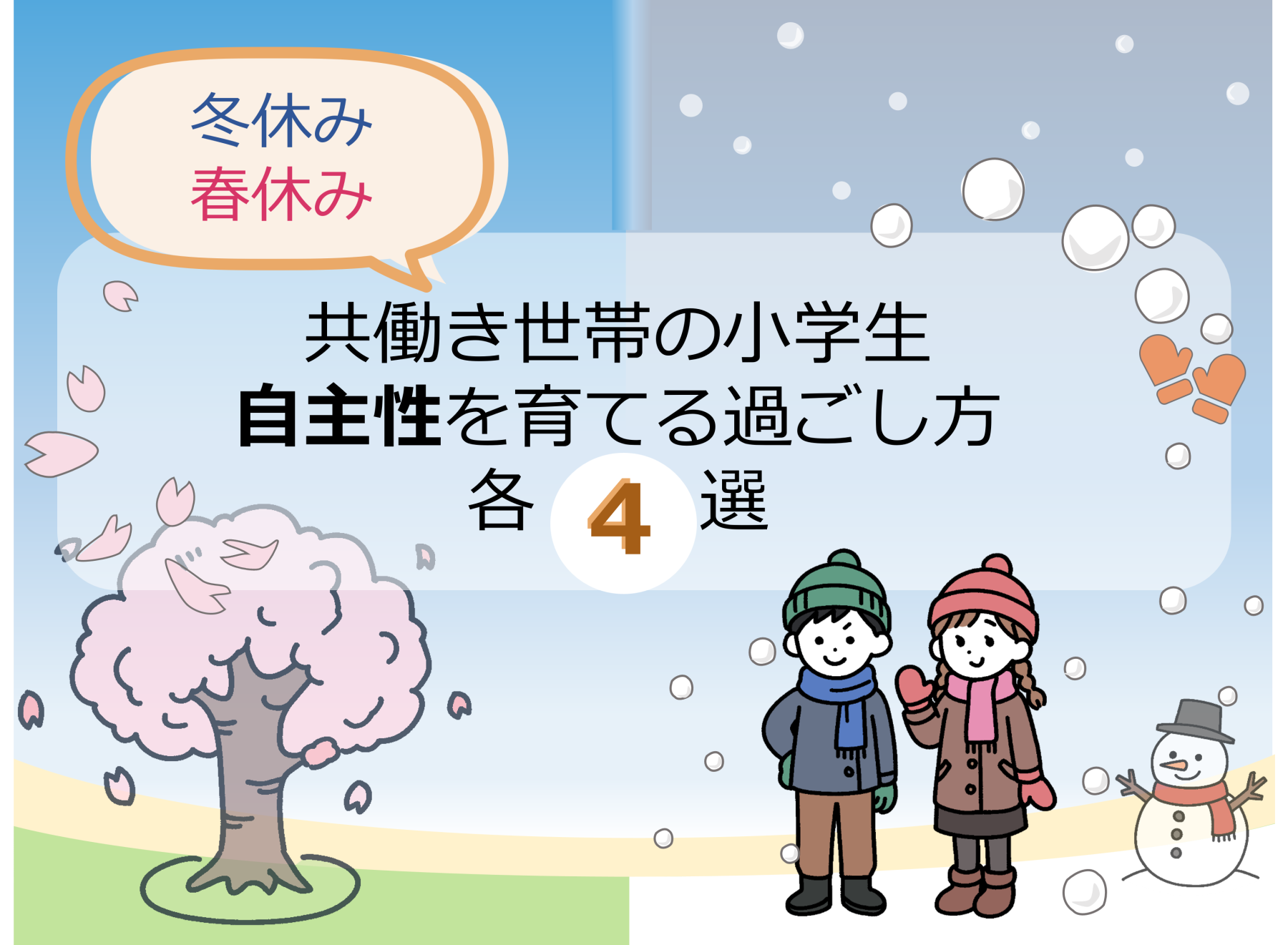
家事と仕事の両立|知る、つながる、働くわたし
【冬休み・春休み】共働き世帯の小学生、自主性を育てる過ごし方 各4選
小学生の冬休み、春休みは2週間ほど。特に冬休みは季節行事も多く、共働き世帯にとっては目まぐるしく過ぎていく期間かもしれません。短い間だけれど、小学生の子どもはどのように過ごせばいいの?宿題はどうやってさせればいい?その時期ならではの体験や、おすすめの学習方法をご紹介します。小学生の冬休みの過ごし方4選学習編|勉強を無理なく進めるコツ宿題のスケジュールを立てる冬休みの宿題で定番なのが、漢字ドリル、計算ドリルと書初めです。学校によっては読書や絵日記など、宿題の内容が変わってきます。冬休み開始と同時に宿題の予定を立て、計画的に終わらせましょう。宿題のスケジュールを組むための具体的な考え方は、次のとおりです。時間がある日に集中して進める朝ご飯を食べた後にすぐ取り組む親がすべて伝えるのではなく、子ども自身にスケジュールを立ててもらうことが大切です。オンライン学習を使って短時間勉強する通信教育などを利用し、苦手項目の克服や新学期に向けた準備をするのも良いでしょう。1日のノルマが設定されていて、1人で学習を進められるため、無理なく効率的に学習を進められます。オンライン学習は採点が不要なものもあり、親の時間確保につながります。生活編|規則正しい生活リズムを保つ早寝早起きを習慣にする「冬の朝は寒くて、なかなか布団から出たくない…」特に冬は、ダラダラと過ごしてしまいがちです。新学期が始まってから体調を崩すことのないよう、冬休みの間も早寝早起きを習慣にしましょう。親が仕事の場合、一緒に朝ごはんを食べるようにすると、生活のリズムが整うだけでなく、親子で過ごす時間も確保できます。親子で体力づくりをする年末年始はごちそうを食べる機会が増え、寒さで活動量が減るため、体力低下や体型変化が気になる時期です。普段通っているスポーツの習い事がお休みの場合は、親子で体力づくりをしてみましょう。一緒に身体を動かすことで、次のようなメリットがあります。基礎体力の向上によって風邪予防になるメタボリック症候群を防げる親子の交流が増える家の周りをランニングしたり、縄跳びや筋トレなどを始めたりするときは、親子で目標を決めて励まし合うと、継続しやすいです。体験編|伝統行事に触れる機会をつくる初詣で参拝する初詣に家族そろって参拝に行くと、子どもは新年を迎える心の準備ができます。大晦日に「この日だけは遅くまで起きてよい」といった特別な約束を作ると、子どもにとって思い出に残る日となります。大掃除で部屋を綺麗にする共働き世帯にとって、少ない休日の中で大掃除するのは大変ですよね。そのような時は家族で大掃除の日を作り、全員で担当を決めて掃除する方法はいかがでしょうか。おすすめは、子どもの担当を自分の部屋と洗面所にすることです。子どもが絵の具容器や習字セットを洗ったあと、色のついた洗面所にがっかりした経験はありませんか?子どもに洗面所を担当してもらうことで、汚したくない心理が働き、大掃除後もきれいに保たれるでしょう。担当を決めたら仕上がりに文句を言わないのが大事なポイントです。みんなで大掃除を終えたあとに外食やスイーツを楽しむ時間を作ると、達成感を共有できて家族の気持ちがまとまります。お正月の料理(おせちやお餅など)買ってきたおせちをみんなで食べる、好きなおせち料理を1品だけ一緒に作ってみるなど、お正月ならではの過ごし方を楽しむと季節を感じられるでしょう。地域のお正月料理を食べる習慣のある家庭なら、子どもに繋いでいく良い機会になります。地域によっては、町内会やショッピングセンターのイベントで餅つき大会が開かれるときもあるでしょう。つきたてのお餅を食べたり、大きな臼でお餅をついたりする体験は、この時期ならではの行事です。家庭では簡単に体験できないため、子どもの視野を広げてくれることでしょう。遊び編|冬ならではの遊びを楽しむ雪遊びやウィンタースポーツに挑戦する冬ならではのウィンタースポーツに挑戦してみるのはいかがでしょうか。家族で出かけて楽しむ以外にも、子どもたちがインストラクターから教わる、合宿プランまで幅広くあります。雪が降る地域では、雪合戦や雪だるまづくりなど、この季節ならではの貴重な経験になります。昔からあるお正月遊び帰省先の親戚とお正月遊びをするときは、次の遊び方がおすすめです。かるた凧揚げこま好きなキャラクターのものを選ぶと親しみがわき、子どもが遊びやすくなります。ことわざかるたなど、勉強につながる遊びもあります。幅広い年代で遊べるため、普段会えない親戚と仲を深められるのも良いところです。小学生の春休みの過ごし方4選学習編|1年間の総復習と準備を進める苦手な科目を克服する次年度に向けて、苦手科目を克服しておくと安心です。通信教育や市販のドリルなどを利用して、1年間の復習をしましょう。キャラクターが入ったドリルを使えば、子どものやる気や集中力の向上が期待できます。本格的な学習に挑戦したい場合は、塾の春期講習に申し込んでみるのもおすすめです。次年度の予習が出来れば、新学年でも良いスタートが切れます。学用品の用意をする1年間使用してきた学用品について、見直しましょう。短くなった鉛筆や色鉛筆に加え、学年が上がると使用するノートのマス目の数も変わります。子ども自身で紅白帽のゴム・のり・セロハンテープなど、文具用品の残りを確認し、必要なものは買い足しましょう。新しい筆記用具を使用することで、新年度への気分も高まります。生活編|新学年に向けて心の準備をする目標を立てる新学年になるタイミングでは、クラス替えや学童の退所など、子どもにとって大きな環境の変化があります。なるべく前向きに過ごせるよう、春休みのうちに新年度の目標を決めましょう。具体的な目標を立てることで、積極的に新しい環境に飛び込みやすくなります。お風呂掃除や洗濯物たたみなどを手伝う宿題が少ないタイミングで、家事を手伝ってもらうのも良いでしょう。学年が上がるため、子どもも新しいことを受け入れやすい時期です。今後も継続したらお小遣いアップなど、ご家庭によって話し合ってみるのも良いですね。体験編|自然や季節行事にふれる時間をつくるお花見で季節を感じる桜の時期に公園でレジャーシートを敷き、いつものランチやおやつを食べるだけでもこの時期ならではの特別な体験になります。仲の良いお友達と、ピクニックへ行くのも良いでしょう。いちご狩りで収穫を楽しむ果物の収穫体験は、自分で収穫して食べることで食育につながります。3月から4月にかけて最盛期を迎えるいちご狩りは、多くの施設で実施されており、家族で取り組みやすい体験です。服装を選ばず、子どもでも収穫しやすいため、初めての果物収穫としておすすめです。いちごの育ち方を考えながら摘むことで、農家さんに対する感謝の気持ちを持てるでしょう。新しい挑戦をする新学年に上がる直前は、お兄さんやお姉さんに近づく意欲が湧いているときです。この機会に、今までにやっていなかった次のような新しい挑戦をしてもらいましょう。子どもだけで買い物をしてみる兄弟だけで電車に乗ってみるもしもの時は親がサポートすることを伝え、子どもの挑戦する気持ちを引き出してみてください。遊び編|春だけの遊びを満喫する春の絶景や自然スポットで遊ぶ暖かく過ごしやすい気候のため、外でのレジャー体験がおすすめです。キャンプや潮干狩り、大きな公園に咲く一面の花畑など、この季節ならではの過ごし方が楽しめます。動物園や牧場にも行きやすい季節で、タイミングが良ければ動物の赤ちゃんと触れ合えるでしょう。自然や動物と関わることで、子どもの精神面が安定しやすくなります。職業体験に参加する共働き世帯の子どもにとって、働く親は日常の姿。職業体験は、将来を考える大きなきっかけになる可能性があります。体験できる職業は、大型の職業体験施設から、各企業が提供するイベントまで幅広くあります。屋内で体験する施設が多いため、花粉症の子どもも安心です。体験には申し込みが必要なケースが多いため、よく調べてから申し込みましょう。親子で体験することで、親にとっても新たな発見が期待できます。番外編|特別な体験を学びや宿題へつなげる身近なものについて掘り下げて考える冬休みは、大掃除に使う重曹などで簡単な実験をしたり、お正月料理や遊びの成り立ちを調べたりすると、季節行事を自由研究につなげられます。季節行事への理解が深まり、親が手伝わなくても自分だけで研究を進められるでしょう。お年玉を通して、お金のことを考えるお正月で子どもが楽しみにしている風習のひとつが、お年玉ではないでしょうか。家庭によって親が預かる、もしくは子どものお小遣いとするケースもあるでしょう。子どもが管理する場合は、お年玉の使い方や使う頻度を話し合うことで、お金について考える良い機会になります。お休みならではの特別な体験を記録する春休みではアウトドア体験で身に着けたサバイバルな知識や、職業体験で得た感覚をノートなどにまとめるのもおすすめです。体験したことを振り返って詳しく調べることで、知識や記憶の定着にも役立ちます。まとめ|今しかできない体験を冬休みや春休みは、家庭の準備も仕事も忙しいことが多く、共働き世帯にとってはあっという間に過ぎてしまいますね。子どもは学年が1年上がるだけで同じ体験をしても見え方や感じ方が変わるもの。その時期ならではの体験をしてもらい、視野を広げてあげたいですね。また、今のうちから学習習慣をつけておくことで、子どもが勉強を進めやすくなるでしょう。この記事が少しでも参考になれば幸いです。関連記事【子育てと仕事の両立は難しい?両立するメリットと押さえておきたいポイント小学生の夏休み、共働きの過ごし方は?タイムスケジュールや夏のイベント情報も!【学童保育】公立・民間の違いから料金まで徹底比較!土曜や長期休暇の利用もOK?